 美しい最期
美しい最期
インド人の70代の男性の死。一人だけずっとずっと泣いていた女性が、患者さんの妻だった。私は死亡確認に行っただけで、死が訪れるまでの様子を知らない。ただ、家族はそれぞれに役割をはっきりさせてケアに関わってきたようで、患者さんの死の後も、全体的に落ち着きがあり、親族への連絡や葬儀屋への連絡などがスムーズにいっていた。悲しみの中にも、なにかやりきった感をともなう清々しさを感じた。部屋にはキッチンから心地よい風が舞い込んでいた。
小学生くらいの孫二人が、「おじいちゃんにさようならを言いたい」と死んだ患者さんのベッドまで来た。親族の中には、死体を見せるのは早すぎると止めようとした人もいたが、家族も親族のほとんどが、「おじいちゃんにしっかりお別れを言いなさい」といった。二人とも、泣いてしまったけど、すぐにお父さんがしっかり二人を抱きしめていた。あぁ、この家族は大丈夫だなと思った。
家で家族を看取るということは、とてもとても大変なこと。特に核家族化の進む今の社会では、本当に大変。このご家族は、仕事をしていない妻が患者さんにつきっきりで、その他家族も普段の日常生活の中で患者さんのケアに大きなウェイトを置いてきたようだった。普段どおり仕事をする者、連絡係となる者、ケアを交代する者、時々様子をみにくる者、自然と役割があったようだ。親族が多く結束も強いと、家族それぞれが役割を担い誰かに全部お任せになることもない。移民の家庭では、お国柄・宗教・文化面も影響するが、家族・親族が一緒にまたはとても近くに住んでいるところが多い。家を出る時、まだ泣いていた患者さんの妻に、「本当によく看取られました。ご自身のされたケアにどうか誇りをもってください、夫の○○さんもすべて感じられていたと思います。」と声をかけたら、泣きながらいっぱい何か言ってくれた。英語ではなかったのですぐ理解できなかったけど、周りの助けがあって「本当に素晴らしい夫だったの」とおっしゃっていたのがわかった。
悲しく美しい最期であったと思う。自分自身の生活、家族とのありかたを強く考えさせられた訪問だった。
死を受け止めること、そして受け入れること
ベトナム人の夫婦。60代前半の男性、肝臓がん。痛みの緩和ができない。訪問は23時だった。眠っていられる時間も長いので、頻繁に痛み止めは必要ないのではと思った。それでも時々あげる声を聞くたびに、妻の○○さんは「夫は痛みに苦しんでいる、どうしていいかわからない」といって、パニックになりそうだった。
患者さんは私が見る限り、痛みの緩和ができていれば最期までお家にいられると思った。でも、妻は「家で死んでほしくない、いざとなったら私一人で看取れるかわからない。とても怖い、できれば病院か施設で医療スタッフが24時間体制でケアする状態で看取りたい」といった。この晩は娘さんがいたものの、一緒に住んでいるわけではなく、仕事にも行かなければならない。。。。育児休暇はあるのに、なんで看取り休暇がないんだろう。。。死んでからじゃ遅いのに。
妻は、自分一人の時に夫が死んでいく過程に向き合うこと、夫が死ぬこと、死自体が自分の目の前にあることが、怖かったのだ。怖いという気持ちと大きな不安が、夫の痛そうな声にあおられて居ても立ってもいられなかったのだ。
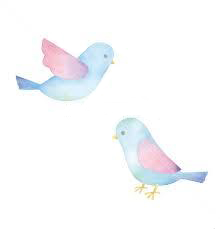
この時の私には、それを察して別の形で家族をサポートするまでに至らなかった。話をじっくり聞き、痛み緩和のためにドクターの指示をもらい、現時点での選択肢を説明したが、あと一歩足りなかった。結局、次の日からクライシスケアというLPN(准看護師)が12時間体制で看護をする処置がとられた。それから亡くなるまでの5日間は看護師が24時間体制で看護。もっと彼女の恐怖をわかってあげられれば、違うアプローチでこの訪問ができたのではないかと自問自答する。在宅ホスピスを始める時に準備できている人もいれば、実際に始まってみないとわからない人も多い。家族の気持ちに寄り添ったとき、その時何が必要かを判断できる力がまだ足りないとあらためて痛感した。
![]() わかばま〜く:プロフィール 1982年生まれ。ニューヨーク州立大学卒業後、 ニューヨーク市立病院に看護師として4年勤務。現在は訪問看護師としてホスピスケアに携わっている。岐阜県各務原市出身。
わかばま〜く:プロフィール 1982年生まれ。ニューヨーク州立大学卒業後、 ニューヨーク市立病院に看護師として4年勤務。現在は訪問看護師としてホスピスケアに携わっている。岐阜県各務原市出身。