
石川憲彦 児童精神神経科医
「誰のつまずき」かをよく整理
子どもは、つまずくのがしごと。つまずくことで、起きあがることを学ぶ。学ぶのは、どう起きあがるかだけではない。つまずかない方法や、ときには同じつまずくならどんな風につまずくのがいいのか、そんなことも学ぶ。何より「順調にいっているときも、つまずいたときも自分は自分でいられる」ということをこそ学ぶ。
つまずいたとき、大人がなすべきことはただひとつ。じっくり自分で立ちあがるのを待ってあげる。けっして手を貸してはいけない。ただただ、ひたすらじっと耐え、忍び、祈るような気持ちで待ちつづける。これが極意だ。周囲の大人の待てる時間が長ければ長いほど、子どもの人間性も、人生の味わいも、深みを増す。
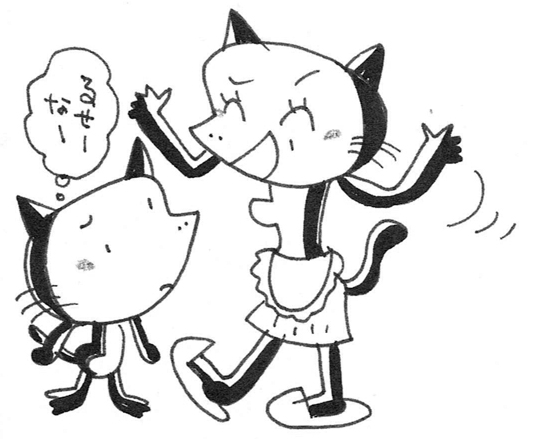
断言しておこう。手助けは、基本的に悪なのだ。
例外はある。子どもの側に事態の解決を期待するのが困難な場合や、大人の側に待つゆとりのない非日常的な事態の場合など、悪とはわかっていても手助けが必要なときはある。ほんとうに必要な手助けは、ときには人間への信頼感を強めてくれるだろう。しかし今日、大人はあまりにもおせっかいだ。不必要な善意を「子どもには解決できないだろう」とか「手おくれになっては困る」とか理屈をつけてばらまく。多少のおせっかいなら、子どもへの愛敬、かえって微笑ましいと笑ってすませられるのだが、ことには限界がある。
いったい、なにが・いつ・どこで、誰にとって・どのような意味で、「誰のつまずき」なのか。
この点をよく理解しないと「いつ・どこで・誰に・なにを・どう」手助けしていいのか、ということも、手助けが「いつ・どこで・誰に・どう」問題となるのかということも、さっぱりわからなくなってしまう。
日常の行きちがいのなかで
脳性麻痺の小学生。担任は「歩行できない。火事のとき、足手まといになっては当人が困るだろう。歩けるようにトレーニングを」と養護学校をすすめる。親は「先生に理解がない。いじめられてかわいそう」と転校を考える。当人は沈黙。しかし20年後、昔をふり返っていう。「歩けないことは苦痛ではなかった。いじめにも慣れていた。ただ、他人と別のあつかいをされること、保護されることは、いまでもいちばん苦痛だ」。
拒食症の高校生。担任は「痩せてつらそう。家族が必要なケアをきちんとしていない」と家族療法をすすめる。親は「注意しても反抗するし、放っておくと食べないし」と娘の反抗を嘆く。そして、当人は「飢えるアフリカのテレビを見ていたら、食べるなんて贅沢できなくなった。でも同じテレビを見て泣いていた親は、番組後けろっとして食べていた。平和教育に熱心な担任には、遠い他国のことより今の自分が大事と諭された。大人になるって、そんなふうにに自分をコントロールすることか。そう思うとこわくなる自分は、最低だ」と自分を罰する。
わかりやすくするために、少し極端な話を選んだ。しかし手助けが、つまずきそのものよりもずっと大きな問題になるという話は、日常のごくありふれたいきちがいのなかにずっと目立つ。
相場がふっとんだ時代に
不幸なことに、今日圧倒的多数の大人は、なんでも早めに手助けしてあげるのがいいことだとひたすら信じこんでいるふしがある。この手助け中毒が進むと、子どもがつまずくこと自体が悪に見えてくる。そしてついには、世間なみでないこと(みんなが漠然とよいと思っていること)以外は、すべて悪と信じこみ、つまずきが起こる前に処理してしまおうと考えはじめる。
いまの若い人たちを見ていると、親も教員もこの中毒への耐性が弱いと思う。自分の判断基準にしたがってものを考えることを、独善的ではないかとおそれる謙虚さが強すぎて、まず周囲を見渡し、世間の判断にしたがって大過なくやりすごそうとする。
ひと昔前までなら、中毒にも救いはあった。まだ世間には、「これくらいは放っておく」というつまずきに対する相場があった。「はしかみたいなもんだ」などと、封建的に「蛮勇」をふるうような差別的な内容ではあっても、相場は社会全体に広く共有されていた。だから世間の判断にしたがっておけば、たいていのことは丸く収まった。相場に異議を申し立てる子どもも、大人になると「まあこんなものか」とやがて納得してくれるのも相場のうちであった。
しかしバブルと同様、相場なんてふっとんでしまった。現代は、つまずきをおそれることが、最悪のつまずきという時代だ。つまずくことへのいたずらなおそれから解放され、いま目の前にいる子どものつまずきを見定めないと、たいへんなつけを払わされる。
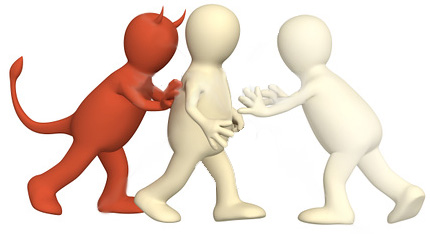
では、どうやって手助け中毒から離脱すればよいのか。

手助けの弊害を明確にすること。いま自分がすすめようとしている手助けは、「何が・いつ・どこで・誰にとって・どのような意味で」最終的には「誰のつまずき」として問題となるのか。この点を、じっくり考えてみよう。この点さえ承知していれば、手助けもやむをえない。あとで手助けが失敗だと気づいても、まだカバーできる。しかしこの点が不明確なら、生命に異常が想定されないかぎり、絶対に手助けはしてはいけない。
100号「学校でつまずかない人生」で伝えたいこと
中毒は手助けをやめれば治る。心配なのは絶対に必要なときにも身動きできない「手助け手抜き症」への悪化だ。
もうひとつ心配なのが、「手助け忖度(差別?)症」。いつの時代にもわが子のためにほかの子の生き方を操作する一部の特権階級は存在する。
「忖度症」と「不能症」。両者は逆方向の社会存在だが、先行きの見えない不安や不満に対して、筋ちがいの攻撃性や衝動性を示すところはなぜか共通する。それが「善意のゴリ押し」や「クレーマー」程度で済めばいいが、いじめ・ハラスメント・虐待などに発展することも多い。
今や「手抜き症」の治療がカギになる。手抜き症の問題は、古い因習に捕らわれて手抜きを開くとか恥とか思うことだけ。脱出するには、「手抜きを責めない」「最低必要限の手助けを明確にして、それはどんな手を使ってでも実行する」のふたつで十分だ。それには「おたがいが気楽に遠慮なく依存し合える双方向性の関係」が、上手に手を抜く極意を見つけるためになによりも必要になるのだ。
いしかわのりひこ:林試の森クリニック院長。お・は編集協力人。著書に『みまもることば〜〜思春期・反抗期になってもいつまでもいつまでも』他。2,018年より『こころ学』シリーズの刊行が始まり、第1巻は『「精神障害」とはなんだろう?ー〜ー「てんかん」からそのルーツをたずねて』(ジャパンマシニスト社刊)。