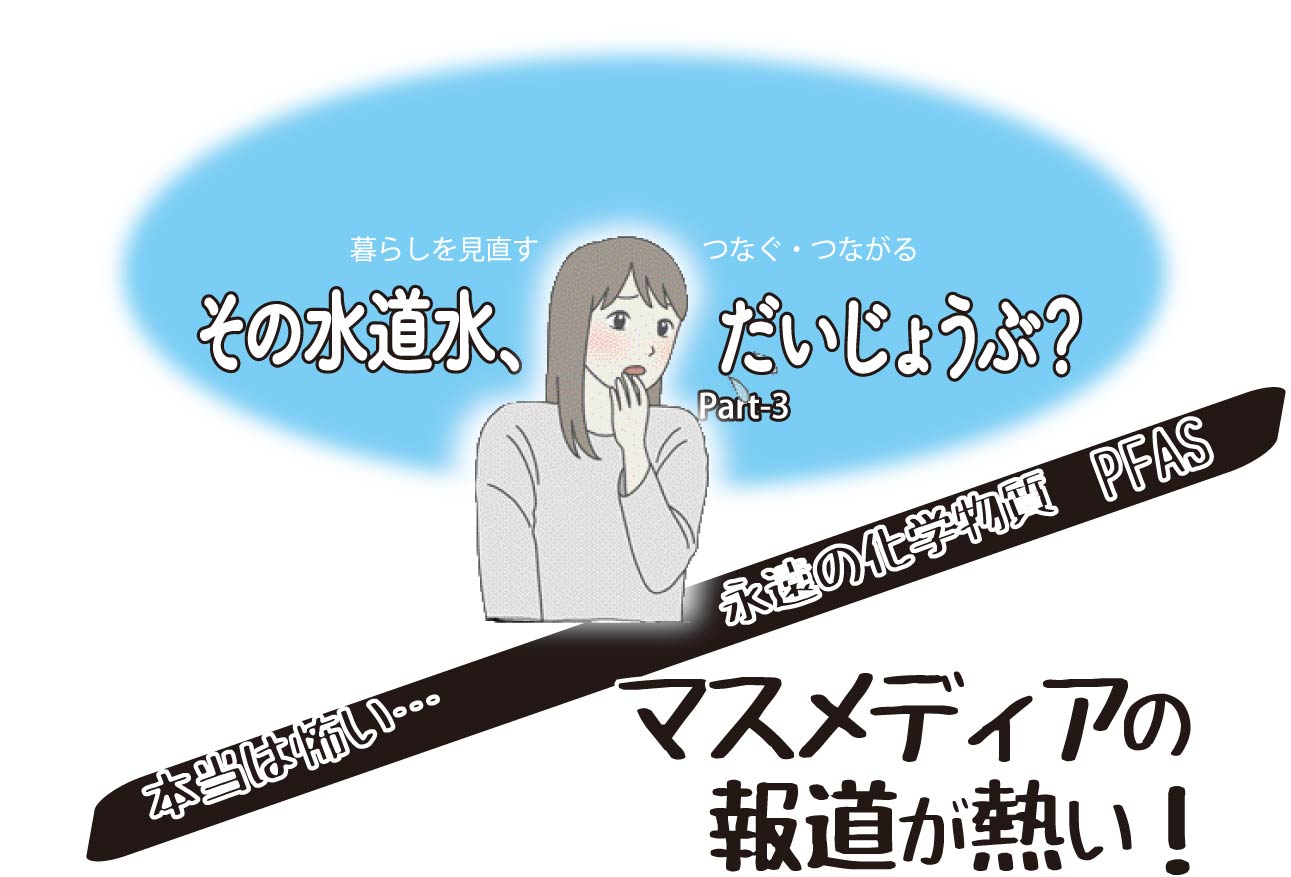発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)を巡り、一部浄水場で高濃度の値が確認された岡山県吉備中央町が25日、住民ら約800人を対象に公費による血液検査を開始した。環境省によると公費での検査は初めて。
山本雅則町長は「5年後も検査をする」と述べ、血中濃度と健康への影響について長期的に調査する考えを示した。
PFASに詳しい群馬大の鯉淵典之教授は、データを蓄積する観点から検出地域での血液検査は重要と指摘。他地域での実施についても「国や自治体が検討する必要がある」としている。日経
検査はPFASの影響を解明し、公衆衛生施策の提案に役立てることなどが目的。今回は12月上旬まで行い、PFAS濃度の他、脂質や肝機能なども調べる。
浄水場の水を継続的に飲んだ約2千人のうち、11月25日時点で18歳以上の成人710人、子ども80人が検査を希望した。25日の検査には50人が参加した。
結果は来年1月中にも検査を受けた人に通知。病気の状況などを尋ねた健康調査票と組み合わせ岡山大が詳しく分析する。この浄水場の水を飲んでいない町民とも比較してPFASによる影響を検討する。
NHKスペシャル
調査報道新世紀
File8 追跡“PFAS汚染”初回放送日:2024年12月1日
自然界で分解されることがほとんどなく永遠の化学物質と呼ばれる有機フッ素化合物PFAS。去年WHO・世界保健機関が一部の物質について発がん性の評価を引き上げたが、そのPFASが日本各地の水道水から検出されているのだ。国が暫定的に定めた目標値を大きく超える地域もあり住民から不安の声が上がっている。汚染源を探る住民、PFASを製造してきた企業、国内外の研究者への独自取材から“PFAS汚染”の全貌に迫る。
ほか、東京新聞、朝日新聞、中日新聞、岐阜新聞からネットニュースにいたるまで、報道は熱を帯びている全国的なPFAS問題。
そんななか、ギャラリーで、「人々の言葉と、言葉にされない思いを紡いだ」という鈴木 萌氏の写真展が開かれていた。
鈴木萌写真展「AABUKU」
京都:2024/5/3-5/12
朝起きてまず初めにコップ一杯飲んだ水
保育園に行く息子に毎日持たせた水
毎朝手ですくって飲んだ湧水
自然農法で育ててきた田芋
グッピーを手で捕まえたせせらぎ
サッカーボールを蹴る学校のグラウンド
卵を投げ入れて拝む池
サップに乗ってのぼる川
目に見えず、匂いも味もしない。その物質はあの時飲んだ水に、手ですくった水に、畑にまいた水に、含まれていたのだろうか。そして今まさに、蛇口をひねって流れ出るこの水にも含まれているのだろうか。体の中に蓄積されたこの物質は、自分に、あるいは子供たちにどんな悪さをしたのだろうか。これからもするのだろうか。
2016年、沖縄県中部に位置する浄水場から本島中南部45万人に供給される水道水が有機フッ素化合物(PFAS)で汚染されていることが公表された。それは自然界や人間の体内ではほとんど分解されることのない「永遠の化学物質」(フォーエバーケミカル)の異名を持つ発がん性物質だった。4年後の2020年、宜野湾市の普天間飛行場格納庫にある火災報知器が誤作動し、大量の泡消火剤の泡が排水溝を通って基地外に流れ出た。ロマンチックにふわふわと漂い、いつまでも消えない泡には高濃度のPFASが含まれていた。そしてそこには、当たり前のように飲んで、遊んで、仕事に、そして拝みに使ってきた水の本当の姿を、昔見たかもしれない「泡」の記憶の断片をたぐりよせながら自分なりに捉えようとしていている人たちがいた。
これは、沖縄における米軍基地由来のPFAS汚染の実態を、人々の水や土地にまつわる記憶を軸に語った物語である。時を遡って汚染の数値を測ることはできず、国も米軍も根本的な解決策を提示しないばかりか汚染の事実さえも認めてはいない。それでも汚染の実態が徐々に明かされるにつれ、今まで気にも留めていなかった日々の記憶に生じる歪み…その記憶を聞き取りながら、汚染された土地と水を歩いた。ふわふわの泡以外に視覚的に捉えることはできない永遠の化学物質。基地のフェンスに遮られどうしても辿り着くことができない汚染源。訪れる人々が気持ちの良い風と波の音を被せ、あえて見ようとしないこの地の重荷。こうして「見えないものたち」は捻れて重なっていた。つかめそうでつかめない、ふわふわと漂う夢のようなあぶくをかきわけるようにして、私は人々の言葉と、言葉にされない思いを紡いだ。 鈴木 萌
鈴木 萌 | プロフィール:東京都出身。London College of Communicationで写真を学び、2011年帰国。主な媒体とる写真を軸に、アーカイブ、イラスト、リサーチ、映像などを織り交ぜ、本やインスタレーションの形で物語を表現する。前作「底翳」は東京、京都、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、北アイルランド、フランスなど世界各地で展示され、同タイトル写真集はLuma Rencontres Dummy Book Award 2021を始めとする世界のダミーブック賞への入選・受賞経験を持つ。
 NHKや新聞、さまざまなメディアから取材をうけた小川さん(PFAS汚染と市政を明らかにする会・代表)にお話をうかがいました。
NHKや新聞、さまざまなメディアから取材をうけた小川さん(PFAS汚染と市政を明らかにする会・代表)にお話をうかがいました。
ーマスコミも取り上げる頻度が高くなりました。PFASを知る人は確実に増えている。でも、当事者よりもマスコミの方が熱意があって市民より怒っているよね。社会的使命というか…。20年後30年後という長いスパンで水資源を考えないと不安ですよ。だって、日本の水って安全で美味しい。特に各務原の水はお墨付きだったし。
この夏に東近江市に行きました。「地域にないものは自分たちで作ろう!」と加工品なども全部自分たちで作る。水と土がきちんとしているということ、これってものすごく大事ですよね。地下水保全条例でもきちんと見える化することが重要です。PFASの問題はどういう分野からでも取り組めます。環境問題、地質問題、地学的にも、あと、健康からもしっかりアプローチできるんですよ。わたし達はもっと危機感を持つことが大事だと思います。“新しい水源地を作るから”とか、“活性炭で除去しているから大丈夫”とか、そういうこととは別に、PFASとはどんなものなのか、知ることが大事ですよね。
鈴木 萌写真展「AABUKU」京都:2024/5/3-5/12を観てきました。ギャラリーでPFASのことを発信していたんです。展示が未だかつて見たことのない方法が用いられて、PFASのことがよくわかり、ちょっとカルチャーショック!こんな展示方法があるんだって。
そこで小川の提案:PFASを逆手にとって、PFASのことが何でもわかる学習館とかつくっちゃう?下の世代に繋いでいくことが大事。だって、PFASはただちに影響は出ないと言われているし、だからこそデータを積み上げ、因果関係がはっきりすることをしていかなきゃ、今は問題ないから知らない、ではいけないでしょ。