 「子どもの体力低下」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、さらに拍車がかかっているようです。この季節は外遊びがぐんと減る時。でも、「子どもは風の子!!」それを意識して外に送り出しましょう!屋外が寒くても、鬼ごっこやドッジボールなど、身体全体を存分に動かす遊びを取り入れることで、じわじわと身体が温まる感覚を知る機会につながりますよ。 また、冬ならではの冷たい空気や息の白さ、氷・霜柱といった現象に興味を持ち、夢中になる子どももいるかもしれません。
「子どもの体力低下」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、さらに拍車がかかっているようです。この季節は外遊びがぐんと減る時。でも、「子どもは風の子!!」それを意識して外に送り出しましょう!屋外が寒くても、鬼ごっこやドッジボールなど、身体全体を存分に動かす遊びを取り入れることで、じわじわと身体が温まる感覚を知る機会につながりますよ。 また、冬ならではの冷たい空気や息の白さ、氷・霜柱といった現象に興味を持ち、夢中になる子どももいるかもしれません。
子どもたちの体力が低下している主な原因は?
運動時間が減少
1日の総運動時間が60分以上の子どもはその他の子どもに比べ体力合計点が高い傾向にありますが、その割合は減少しており、特に男子の方が顕著に減っています。中学高での部活動の減少も手威力低下の一員と考えられます。
スクリーンタイムが増加
平日1日あたりのテレビ、スマートフォン、ゲーム機等による映像の視聴時間が長くなる傾向があり、学習以外に2時間以上見ている割合が増加。特に男子で長時間化しています。これが運動時間の減少にも繋がっていると考えられます。新型コロナウイルス感染の影響を受けて、放課後の遊びや休日の外出なども含めた子ども達の行動・運動が制限されたことが、それまでの傾向に拍車をかけたといえます。
子どもに最低限必要な運動量は「1日60分」
日本スポーツ協会による「子どもの身体活動ガイドライン」では、子どもとって最低限必要な身体活動量は「毎日60分以上」とされています。
これはいわゆる「スポーツ」だけに限らず、身体を使った遊び、 生活活動なども含めた時間なので、たとえば保育園や幼稚園の行き帰りに少し遠回りして散歩してみたり、家の中でも遊びに体操やダンスのような動きを取り入れたり、掃除などの家事を手伝わせるなど、いろいろな形で運動量を増やす工夫ができます。
子どもの体力をつけるために必要なこと
【運動】外遊びや家の中でできる軽い運動からはじめる
例えば、食事の支度や後片付けの手伝いで少しずつ重いものを運んでもらったり、遊んでいる時の姿勢を意識するように声をかけたりするだけでも、毎日の積み重ねで運動の機会を増やせます。歌が好きな子には踊りながら歌ってとお願いする、できるだけ思い切り体を動かせる公園などに連れ出すなど、様々な場面で体を動かすことを意識をすると良いでしょう。
【食事】肉・魚・卵などたんぱく質をバランスよく
なかでも意識したいのは、筋肉の成長に必要なたんぱく質。小学生は1日30〜50g、成長期では60g以上のたんぱく質が必要といわれています。
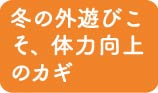 はやい段階で、外遊びを楽しむ習慣を身に付けていることは、生涯にわたっての豊かなスポーツライフを実現するための素地になります。
はやい段階で、外遊びを楽しむ習慣を身に付けていることは、生涯にわたっての豊かなスポーツライフを実現するための素地になります。
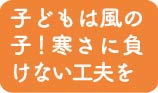 「外は寒いから、温かい教室にいたい」「外に出たくない」というのは、自然な感情です。外から帰ったら、手洗い・うがい・水分補給等も忘れずに。
「外は寒いから、温かい教室にいたい」「外に出たくない」というのは、自然な感情です。外から帰ったら、手洗い・うがい・水分補給等も忘れずに。
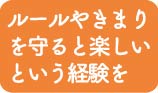 「鬼ごっこ」という遊び一つとっても、子どもたち一人ひとりが考えるルールには、小さなズレがあります。そのズレを修正して、みんなのルールを作ることが大切。小さなズレをそのままにしておくと、うまく仲間に入れない子が出てきたり、言い争いになってしまったりすることも。ルールの共通理解が、みんなで楽しく遊ぶことにつながります。
「鬼ごっこ」という遊び一つとっても、子どもたち一人ひとりが考えるルールには、小さなズレがあります。そのズレを修正して、みんなのルールを作ることが大切。小さなズレをそのままにしておくと、うまく仲間に入れない子が出てきたり、言い争いになってしまったりすることも。ルールの共通理解が、みんなで楽しく遊ぶことにつながります。
 具体的な遊びを2つ紹介します。
具体的な遊びを2つ紹介します。
へびじゃんけん
人数:5~10人くらい
遊びの時間の目安:5分
2チームに分けて、先頭の子が線の上を走ります。途中で、相手と出会ったら、タッチしてじゃんけんをします。勝った子はそのまま進み、負けた子は戻って自分の陣地の一番後ろに並びます。それを繰り返し相手チームの陣地に入ったら勝ち。
おしくらまんじゅう
人数:5人くらい
遊びの時間の目安:1分
腕を組んで背中を合わせて円になります。「おしくらまんじゅう押されて泣くな」と歌いながら、肩を寄せて押し合います。体と体をくっつける面白さを感じたり、ギューギュー押すことで体の温まりを感じたりすることができます。子どもたちの円陣の外側に円を描き、押されてはみ出してしまった子は、アウトになるルールにすると、さらに盛り上がります。