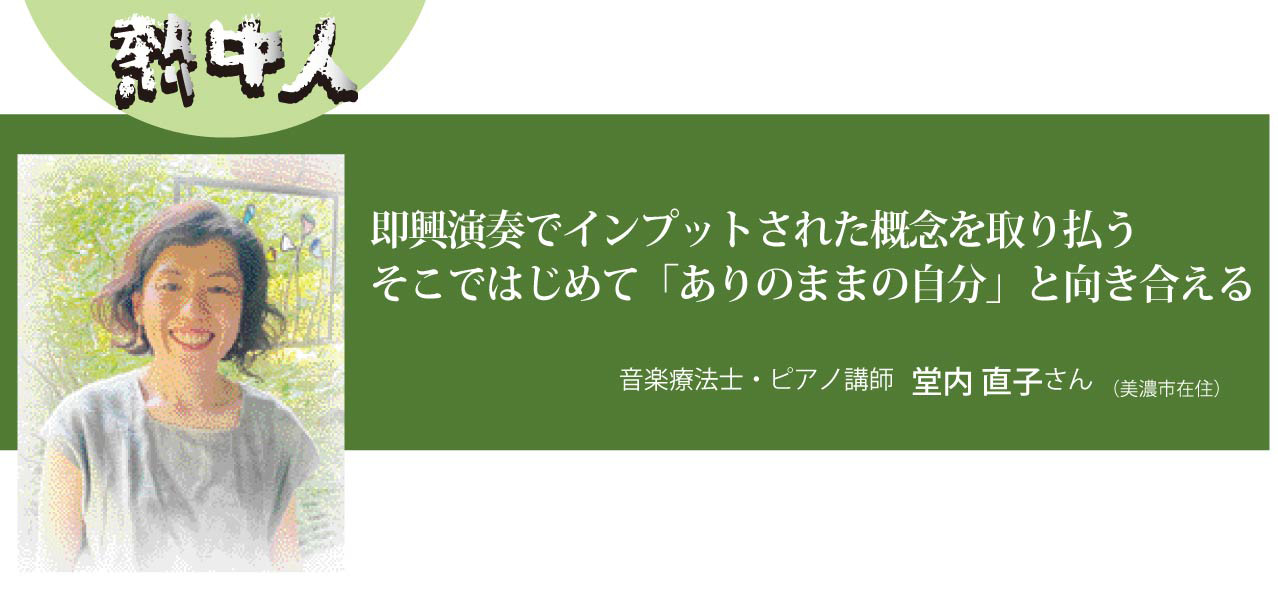 音楽療法とは?
音楽療法とは?
分野も、流派もたくさんあって、学ぶ国によっても違います。「クライアントが音楽を聴く」が受動的音楽療法で、「音楽をする」のが能動的音楽療法。私は、形態学的音楽療法(注1)をドイツで勉強しました。
形態学的音楽療法では何をするのかというと、即興演奏です。即興は楽器を弾けなくてもできます。叩けば音が出るような楽器をたくさん用意します。木琴とか鉄琴もどれを鳴らしても不協和音が出ないようにペンタトニック(全音階)のものを使います。手さえ動かせば綺麗に音が出る。そういう楽器を一緒に演奏します。虐待を受けているクライアントとのセッションの録音を、たとえば、全くなんの情報もなく演奏を聞くと、叩かれているような気がしたなどと、聞いた人がみんな同じような感想を述べ、そこから紐解いていきます。音楽は言葉が要らないので、患者さんが言えない事も音に出てきます。
そこから療法士に?
はい、音楽大学って選択肢があまりなくて。日本の大学卒業後に音楽教室に就職することが決まり、4月から社会人スタートの予定でした。ところが、3月にピアノの師匠がドイツに演奏旅行に行くことになり、何人か生徒を連れてってくれたんです。演奏させてもらえる機会もあって、ホームステイもさせてもらえた。それがとても楽しくて、ドイツってなんて素晴らしい国なんだと思いました。ドイツ滞在中のある日、散歩している時に「そうだ!音楽療法だ」と思いつき、その足で図書館に行きドイツで音楽療法を学べる学校を調べ、その後留学しました。
大事なことは「待つ」こと
音楽療法は教育ではありません。その人を支えたり、生きていくのをサポートする…そういう方向性があります。私のドイツの師匠が音楽療法で一番大事なのは「待つこと」と教えてくれました。我が子には難しいですが、ピアノの生徒さんには待つことができます。
大人の方はみなさん本当に熱心です。ご自分のためにやっている方が多いので、すごくまっすぐで、感動しますね。92歳でバイエルを弾かれた方のお話をお聞きしましたが、その方の人生が音に出るんですよ。本当に、上手い下手とは関係なく、音楽に滲み出るものがあります。
支援から改善
たとえば、発語のない子が、発語できたり、喋れないけど、歌だと歌える、とか。そもそもコミュニケーションが難しい方が、音楽を介すとできることもあります。
高齢の方は、まずは生活の質を高めるのが一番です。あとは人との交流ですね。やったことのない楽器を一から始めることは、皆さんすごく生きがいを感じるらしくて。難しいですが、それを克服する力がおありなので、ピアノでも弾けるようになっていきます。
概念をひっくり返す
『即興』がその人の先入観を取り払うのに役立っているかもしれないです。即興においては出した音すべて○なんですよ。約束事は一つだけ。一緒にセッションしている中の一人でも「ストップ!」と言ったらやめること。(たとえば大きな音をずーっと鳴らし続けたり)そこにいる人がみんな心地良くなれたらオーケー。黙って座っていてもいい。終わるのも自由。全員が終わりたいなと思った瞬間におわる・・・すごく長くて、セッションの時間だいじょうぶかな、なんてこともあるけど、それでも待つ。気が済んだら終わることが分かっているから、待つんです。即興って、自分が出したい音を出すことだから、今、本当に自分のしたい事って、何?そんな問いかけにもなります。
生の芸術・アール・ブリュット
わたしは、アール・ブリュットという分野がすごく好きで、なんでこんなにビシビシと伝わってくるんだろうって。ピアノもそうだけど、技術が卓越していること以外の演奏からすごく伝わってくるんです。それは一体なんなんだろって。巨匠のコンサートに行けば、もちろん感動はしますよ、それとは全く別の種類の感動なんですね。それは、音楽療法を学んだこととも大いに関係があると思っています。
そもそも音楽療法を学んだのも、精神病院でボランティアをしていたことがきっかけだったんです。作業療法士と患者さんたちと一緒に歌うサークルがあって、週に一回、10人くらいで歌うんです。すごくいろんな薬を飲んでいらっしゃって普段は鬱な感じの方や、ハイになると人を殴っちゃうとか、そういう方ばかりのグループでしたが、音楽をやっている間はそんなことは一切なくて、音楽の力って凄いなって思いました。そしてアートはいいなって。全ての人に無限の可能性があると信じて活動しています。
(注1)形態学的音楽療法(音楽の形態(構造)を分析し、それをクライアントの心理的・身体的な状態に合わせることで、治療効果を高める音楽療法の一形態。主にドイツで発展し、音楽の構造的特徴(リズム、ハーモニー、メロディーなど)が、人の感情や身体機能にどのように影響するかを研究・応用する)能動的・受動的アプローチ:歌唱、楽器演奏、即興演奏などの能動的な音楽活動だけでなく、音楽を聴く受動的な活動も行う。音楽の持つ力を最大限に引き出し、クライアントのQOL(生活の質)向上に貢献する治療法)