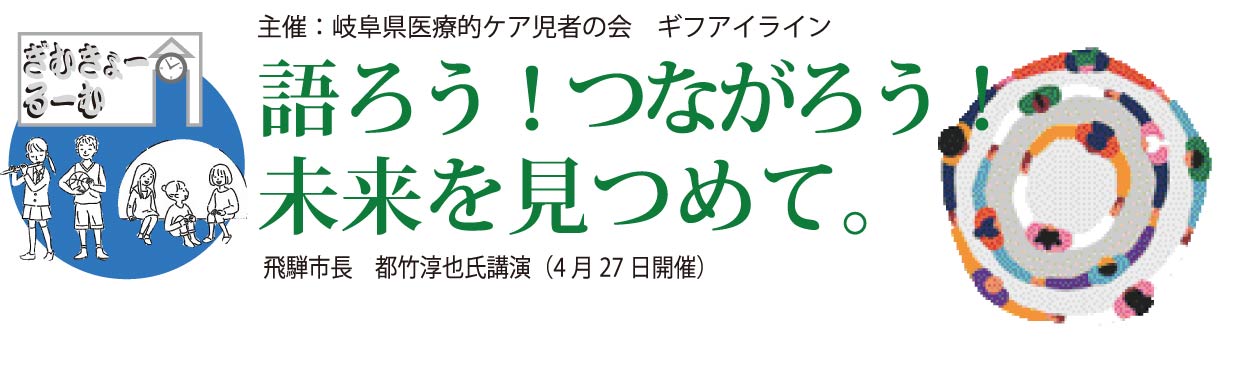 後半:行政ができること
後半:行政ができること
日本の障害者総合支援法と児童福祉法の体系として、児童福祉法までは発達の支援をしますが、障害者総合支援法、つまり大人になると、発達支援の考え方が入ってない。そこが一番問題だと思っていて、今、飛騨市内のB型の作業所で発達支援の取り組みをいれた、B型生活介護の事業を展開して、飛騨市はC型就労継続支援事業と名乗っています。これを国に対して、発達支援とは、生涯発達して成長していくんだ、ということを制度として保証する仕組みを考えて欲しいと提案しようと思っています。
行政の仕事で障がいに関わる仕事で大事なのは共感なんですよね。職員がいかに共感をできるかです。実は一番共感してもらいたいのは、こういう気持ちを辿って今ここに至ってるってこと。その中で家族は救われていく。受容していくと同時に救われていくわけです。
家族が救われるポイント
1つは「この子はこの子なりでいいんだ」で、「うちもどこにでもある普通の家族なんだ」と認識させてくれる人たちの存在。これが僕は非常に大事だと思います。それから、困難な状況でも、笑顔で明るく支えてくれる人たちの存在。そして悩みを共有できる仲間の存在。これが、僕は家族を救ってくれると思っています。
うちの子も、「しょうちゃん」って固有名詞でみなさんに呼んでもらえるんだっていうことがわかったとき、とっても嬉しかったんです。
この子はこの子のままでいいんだ。もう充分障がいを受容できている家族でも、やっぱりあるときふっと弱くなってまた同じような気持ちになるんです。その時に明るく支えてくれる人が周囲にいることで、どれだけ支えられ助けられてるか。
大きな転機
平成18年。次男の障がいがわかった頃のことです。発達支援センターですごい待たされたことを県庁の重点政策協議で話題にしたら当時の県庁の健康福祉部の幹部に「公私混同だ」と批判されました。でも、その時に後に副知事になる部長さんが「ちょっと何かできんか調べてみる」って言われたんです。その結果、翌年度の当初予算に各地域の医療機関に発達障害の専門外来を設置した場合に補助を出す発達専門外来診療促進事業に630万の予算がつきそれが新聞に載ったんです。この時本当に嬉しくて。何で嬉しかったっていうと、うちの子がとった予算だから、そう思ったからです。うちの子がいなければ僕はこれを言っていない。630万がつかなかったとしたら、救われずに長く待つ家族はもっと増える。なので、次男が世のため人のために役立ったことになる。
うちの子は、自分で自分の生活をしてくってことは不可能です。けれど、この子の存在を親が違う形に転換させてやることができれば、この子が世の中の役に立ったことになる。それが自分が子にしてやれることだ。これが僕自身にとっての大きな転機になりました。
先人たちが切り拓いてくれたからこそ今がある
びわこ学園創始者の糸賀一雄っていう先生の「この子らを世の光に」っていう言葉。みなさんも聞いたことあると思います。「この子らに世の光を」ではなく「この子らを世の光に」。びわこ学園は、重度心身障害の子どもたちを、日本で初めて受け入れた施設です。創始者の糸賀一雄先生がもう一つ名言を残しておられた。「自覚者が責任者である」。つまり、課題に気がついたら、気がついた人間が率先してその課題を解決するために取り組む責任があるんだ、ということです。
実際に障害者支援の世界を切り開いてきたというのは、多くの先人たちが何とかしようって、誰かに頼るんでなくて自分で何とかしようと思って切り開いてきたことの積み重ねで今があるんです。
障がい児医療ということに携わることになり、平成25年の4月から地域医療推進課です。福祉課じゃない、医療課です。医療課だからこそ医療の面から障がいの分野にアプローチすることができる。そして「障がい児・者医療」という言葉を提唱しました。政策の手始めは短期入所、ショートステイの拡充ですが、これがなかなか広がらない。なぜか。要は、短期入所者は福祉サービスであって、医療機関がするべきことではないという意識があったからなんです。
それから小児在宅医療。全国を回ってどんどん取り込んでいる。ところが、なんかおかしい。在宅支援のイメージがわかないんです。実は、職員が現場に行けてないんですね。個人情報保護法がハードルとなっているんです。ですが、これが問題だと思ったことを対策をすれば必ず政策になるんです。
平成28年 飛騨市長に
県や市の職員に、もっと現場に行ってもらいたい。で、課題を感じて人と語って、なんとかしないといかんっていう強い思いを持つ。そこからかならず施策は広がってきます。それ以上に市長や町長、担当者に現場に来て見てもらいたい。どんな生活をしているかを見てそれに反応する人が一人でもいたら、そこが変わるきっかけになります、必ず。役所っていうのは多くの仕事を抱えていますから、個別に現場には行かない。そんな中で私平成28年、縁あって飛騨市の市長になりました。飛騨市の障がいの考え方は「『自分のやりたいことがやりたいようにできないこと』これが障がいである」。
障がいというのは法律があります。こういう状態こういう障がいでと、認定をしてもらい手帳が出るというのが普通です。これはあくまでも法律上の話。「やりたいことがやりたいようにできない状態」これを「作業遂行障がい」って言い「やりたいことをやりたいようにできるようサポートすることで障がいは消える」ということです。逆にいうとこれは障がいの認定があろうがなかろうが関係ない。対象者は何らかの生きづらさを感じる人全てだとという考え方です。
法律ができたから解決とはならない
例えば、私はメガネをかけています。メガネを外すと多分どこかでつまづく。でも、私は視覚障害ではありません。なぜか?眼鏡があるからです。つまりサポートできるサービスとか、サポートされるデバイスがあれば、障がいじゃなくなるんですよ。これをみなさん理解する必要があると思うんです。で、逆にこういう考え方に立つと、全てが視野に入ってきます。つまり弱い立場の人たちが、全て視野に入ってくる。強い個性とか生まれつきのハンディーを持っていても生き生きと暮らせるように、そのための支援をしていくという考え方。ですから、本人も周りも障がいになるものを双方の立場から乗り越えたり、なくしたりすることで障がいを減らしていくというのが飛騨市の障がいの考え方の根本です。
医療的支援法ができて良かったね。法律だけできたら全部解決するなんて思ったら大間違いですよ。市町村が動かないことには、法律ができたって何にも進まない。一番大事なのは市長なんです。
問題の裏に潜む原因
小学校の事例でいくと、登校、行き渋り、不登校に…。A君はすごく運動が得意。ところがサッカーでつまずいて、試合になるとパフォーマンスが落ちて監督からも怒られモチベーションが下り不登校になった。で、作業療法士に見立ててもらったら空間認知が苦手なのがわかりました。サッカーはフォーメーションですから、体を動かすのが得意でも、空間認識ができてないと動けないんです。事前に盤上で人の動きを確認して監督にもマグネットを使って、こう動くんだよとやってもらうとサッカーにまた集中できるようになって不登校が解消された。という例。
もう一つの事例、定規を使ってもうまく線が引けないっていう先生からの相談。発達性協調運動障がいの状態ですね。簡単に言うと縄跳びとか字をうまくかけないっていう不器用さです。ところがこれ診断つかないですよ。そうすると不器用な子だけで終わるんです。どうかすると自信をなくす。どうすればいいか。自分で作戦を立てるんです。作戦を立てるときに作業療法士がちょっとアドバイスをいれるんです。この子はどういうアドバイスを受けたかというと、視覚で定規の線がチカチカして見えてしまうことが問題と気づいたので、線のない透明の定規で厚みのある定規を使ってみようって。それで線が引けるようになり、自信がついて他のこともうまくやれるように。
行政の役割
最後に行政の最優先したその先はなにか。自分の力で暮らしていくことが困難な立場にある人を支援することが、行政の一番やるべきことだと思っている。ともすると今日ここにお見えになっている皆さんは私もそうですが、自分の子どもさんが障がいがある、あるいは、関わってらっしゃる方が多いと思います。自分の身近に障がい者あるいは病気の人もいないと他人事ですよね。するとなんで福祉にそんなに力を入れるの?って。その度に、これは明日のあなたのことですって言うんです。皆さんが今日帰られる時事故に遭うかもしれない、事故で下半身不随になるかもしれない、自分に何か起こっても誰も助けてくれないことを想像してみてください。誰かが必ず支えてくれるという社会を作る。だからどんなことでも全て自分ごとなんです。そのために困ったこととか、辛いこと、大変なことがあった時に「困っているんです」「辛いんです」「大変なんです」と言っていいんだという雰囲気を作る。誰かが受け止めるという社会を作る。お互い様ですからって必ず誰かが助けてくれる。そういう地域を作る。そのために市町村との役割がある。そして不安と戦うご本人とご家族に「何も心配はいりませんよ。安心してくださいね」と心の底から言える地域を作るのが私の夢です。そんな思いて、弱い立場の方々や障がい児者の支援に取り組んでいます。
文責/にらめっこ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー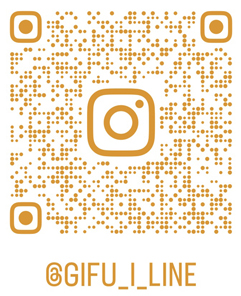
ギフアイラインは会員登録された方へ全国や岐阜県内の医療や福祉、教育などの情報をお届けしています。「医療的ケア児支援法」が施行された時に「全国医療的ケアライン」と共に会を立ち上げ、現在会員は岐阜県内200名を超える会となっており、医療的ケア児(医ケア児)・重症心身障がい児(重心児)家族だけでなく、ご支援者の方にも会員になっていただいております。会員になるには、公式LINEに入っていただくだけで、無料で情報を配信しております。Instagramもありますので、そちらも是非ご覧下さい。