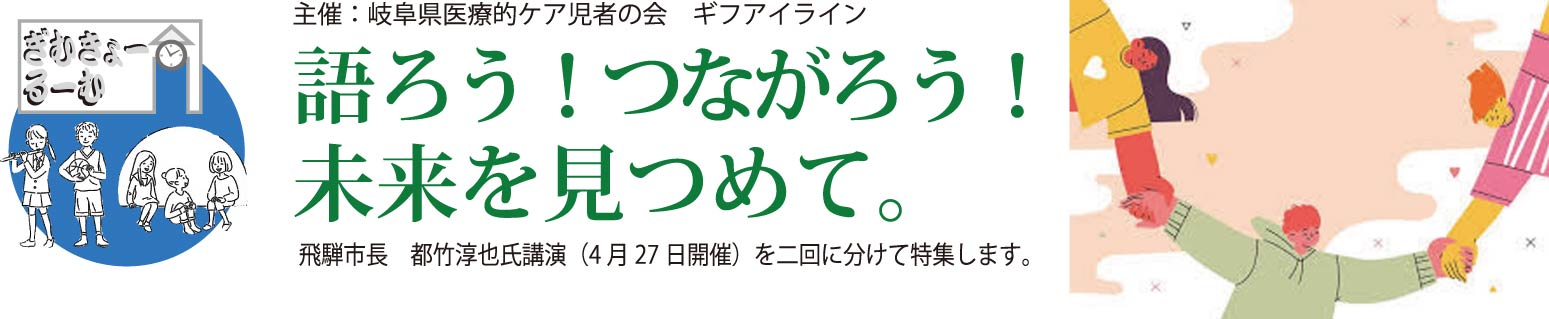 「医療的ケア・障がい児者が安心して暮らせる地域づくりに向けて」
「医療的ケア・障がい児者が安心して暮らせる地域づくりに向けて」
前半:次男の障がい
飛騨市もいま、学校作業療法とか、地域生活支援センターとか、全ての子どもたちから大人たちの支援をしていく取り組みをやっています。私の障がい者支援というものに対する考え方とか、これまでの自分自身の取り組んできたこと、そのあたりをお話ししていきたいと思います。
頭ではわかっていたが…
平成28年3月に飛騨市長になりました。次男は重度の知的障がいを伴う自閉症です。今20歳で療育手帳A1。発語は今でもなく、まったくしゃべれません。コミュニケーションはほぼとれていません。こだわりが結構強い。1歳半の時にちょっと言葉遅いなとか、ちょっと他の子と違うんじゃないかな、もしかしてこの子には障がいがあるんじゃないかって、ふっと思いました。その夜、なんとなく自分の体温がすーっと抜けていくといいますか、そういう感覚。気になってネット調べてみると、「あなたの子どもが自閉症である確率は80%です」とでてきた。で、夜もねれない。その当時は県庁勤務でした。そこに、健康局長・小児科のドクターがおられたので相談に行きました。ちょうど発達障害支援法ができた直後でした。
ドクターからは、「発達支援センター『のぞみ』に行って相談してください」と言われました。で、電話をしたら相談まで3ヶ月待ちだって!不安で夜も寝られないんですよ、それなのに3ヶ月待ち。これは地獄…本当にそう思いました。3ヶ月後、作業療法士の先生がとにかく医師の診察を受けることを薦められ、結果として惠光学園に通うことになったんです。知的障害児母子通園施設と書いてあるパンフレットをもらい、「そうか、うちの子は知的障がい児なんだ」ってことをその時に思いました。
障がい児、障がい者を違う扱いをしてはいけないことを頭でわかってはいたけど、何か世の中の、暗くて硬〜い場所に自分と自分の家族が来てしまったという、そんな思いを正直持ちました。しかし、惠光学園では本当に救われました。明るい先生たちがちゃんと次男を受け入れてくれる。そしていつも笑顔のスタッフさん。なによりも同じ境遇の親たち。本当にどれだけ救われたかしれません。
そんな時、長男がお世話になっている幼稚園から「特別支援の体制をとるので、うちに来ませんか」というお誘いがあって、1年半経ったところで、幼稚園に転入しました。しかし、幼稚園ってところはやっぱり集団教育なんですね。例えば発表会。鼓笛をやろうと思っても鼓笛隊がわかりませんし、教えてもできませんから、途中で横からさっと出てきて、さっと出て行く。動物園に行けば、うちの子身体に問題はないのですが、連れて歩くのが大変じゃないかということで車椅子…これが先生ができる精一杯のサポートなんですね。
正直言ってその頃は、どれくらい発達しているのかわからないんですね。ですけど、やっぱり思ったほどは伸びていなかったんですよ。そりゃそうですよ。今二十歳になっても発語もないし、コミュニケーションも取れないわけですから。
悩みや困りごとを共有できる安心感
インクルージョンっていう概念は随分進みましたけど、まだまだ世の中で取り組み始めたばかり。先生たちも試行錯誤、親も試行錯誤です。集団の中では同じことを、同じように…うちの子はやっぱりできません。
惠光学園で、同じ境遇の子たちと一緒に同じような感じでやっていた方がよかったんじゃないか。そう思っても、惠光学園へは戻れない。あそこは一回出てしまうと戻れないんですね。そうなるとここは、親の考え方次第です。自分が「障がい」というものの見方を形成することになったのはこの頃かな。だから、高等部は迷わず岐阜特別支援学校に入学を決めました。日本の特別支援教育って個々に応じた対応が徹底した教育システムが成り立っているんです。それともう一つ大事なこと。それは特別支援学校は最初から将来どうするのかを考えて取り組んでいること。それと、何といっても悩みや困りごとを共有できる同じ境遇の親の存在があるってこと。これがどれだけ救われるかということです。
当事者じゃないとわからないことはたくさんあります。悩みを共有できることは素敵なことです。小学部・中学部・高等部と進学して行くんですが、少しずつ様々なことが理解できるようになる。それでも新しい問題も出てきます。今、高等部を卒業して生活介護の事業所に行ってるんですが、人間って生涯ずっと発達していくんだっていう思いは持っていたほうがいいです。
覚悟
僕はね、親が元気でいると思っちゃダメだってずっと言ってるんですね。県庁時代から「高等部卒業したら親は死んだと思え」こう言ってるんです。
高等部卒業して、自分がこの子を人生ずっと面倒見ていくんだと思うほど子どもにとって不幸なことはない。自分はいない。自分の配偶者もいないっていうときのことを考えて体制を整えることがいかに大事かって言ってきました。
親は意地をはるんですね
というのも、ちょうどその時同居の母親が末期の癌で、在宅医療を受けてる時だったんです。ですから当然母親は全く頼れない。で、私この仕事です。自由な時間はほぼないんですよ。夜もびっしり会合が入ってる。県外出張、東京出張が多い。全く自分の自由がきかない中で、嫁さんいない。そうするとどこかで預かってもらうしかないんです。
最初ね、ショートステイでもちょっと難しいって言われたんですよ。で、そうなった時に親って意地になる。意地になるもんですから、「もう俺公務休んでやったるよ!」ってこう思いました。もう3時以降の日程は全部キャンセルで、出張も行かないで、自分で面倒をみるって思ったんです。そうしたら相談支援専門医の人が、「もう都竹さん、気持ちはわかるけど、こういう時だからこそサービスに頼った方がいいですよ。都竹さんが頼ることが、後の人の道を開くかもしれない。だからここはとにかくサービスに頼って」と普段僕が言ってることと同じようなことを僕に返してきまたんです。当事者になってみますとね、口ではいろんなことを言いますけど、でもやっぱりいろんなことがあるんだなって思いましたね。
障がいを受容するということ
もう一つのハードルは障がいの受容だというふうに思います。障がいの受容って死の受容と一緒だってことを思うんですね。
キューブラー・ロスっていう人が「死ぬ瞬間」って本を書いてます。これは有名な本で、私これを学生時代に読みました。1970年代に書かれた本ですが、末期のがん患者にたくさん取材をして、自分が余命いくばくもないと言う宣告をされたときに人はどういうプロセスをたどるか、ということを研究した本で、キューブラー・ロスは死の受容は5段階だと言います。 まず否認。その次に怒り。次に取引という段階があります。取引とは、神様仏様にお参りに行ったり、何かいいサプリメントがないかとか、何かいい薬がないかとか、何かこういうまじないをすれば治るんじゃないかとか、こういうことをやるのがこの取引という段階です。次に抑うつという段階。ずっと落ち込んで暗くなって鬱状態。塞ぎ込んで誰ともしゃべりたくない。そんな状態になってきて、その後だんだんだんだん緩やかに自分の終焉ってものを見つめることができる、受容の段階に至るというのがキューブラー・ロスの死の受容5段階モデルです。
で、我が子に障がいがあるという事実に直面した親も、私は同じ5段階をたどるというふうに思っています。しかも、これが一回で終わらないです。何回も起こります。人生のいろんなライフイベントの都度起こる。例えば、子どもが小学校に入る。近所の子ども達はみんなランドセルをして集団登校でいく。うちの子どもは行けない。振幅の差は小さいけれどもやっぱり同じようなことが起こると私は思います。障がいの受容って本当に大変なんだってことなんです。行政の仕事で障がいに関わる仕事、もちろん、私も今この立場でやっているわけですけど、大事なのは共感なんですよね。
次号は「行政のあり方について・飛騨市の取り組み」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
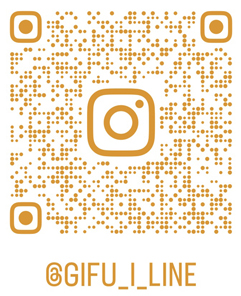 ギフアイラインは会員登録された方へ全国や岐阜県内の医療や福祉、教育などの情報をお届けしています。「医療的ケア児支援法」が施行された時に「全国医療的ケアライン」と共に会を立ち上げ、現在会員は岐阜県内200名を超える会となっており、医療的ケア児(医ケア児)・重症心身障がい児(重心児)家族だけでなく、ご支援者の方にも会員になっていただいております。会員になるには、公式LINEに入っていただくだけで、無料で情報を配信しております。Instagramもありますので、そちらも是非ご覧下さい。
ギフアイラインは会員登録された方へ全国や岐阜県内の医療や福祉、教育などの情報をお届けしています。「医療的ケア児支援法」が施行された時に「全国医療的ケアライン」と共に会を立ち上げ、現在会員は岐阜県内200名を超える会となっており、医療的ケア児(医ケア児)・重症心身障がい児(重心児)家族だけでなく、ご支援者の方にも会員になっていただいております。会員になるには、公式LINEに入っていただくだけで、無料で情報を配信しております。Instagramもありますので、そちらも是非ご覧下さい。