非常時に役立つもの

<テント>災害用に用途を限定して持っておくより、“普段は遊びで使いながら、いざというときには住居にもなる”という意識で、使いながら備えておくことがベスト!
・水のたまりにくい場所を選ぶ→日よけ、雨よけのために、木の下も選択肢のひとつです。ただし、落雷の危険がある場所は避けてください。
・入り口は風下側に→入り口が風上を向いていると、突風で風をはらみ、飛ばされる危険あり。
・必ず張り綱を張る→張り綱を張らないと、大人2人が中にいても飛ばされることが。
・すのこやパレットを利用→床を上げることで、浸水・湿気・冷えを抑えられます。
・タープを張って生活空間を広げる→タープがなければブルーシートで代用してもよい。
・雨水は生活用水に→タープにたまった水は捨てずに利用。
・生活テントと物資テントを分ける→テントの数に余裕があれば、用途で分けると暮らしやすくなります。
・避難所のひとつとして認めてもらう→行政に働きかけます。認められれば支援物資や情報を受けやすくなります。
<携帯トイレ> 登山などのアウトドアに出かける際にも持参を呼びかけているアイテム。
少しでも自然への負荷を減らしたり、水場の水を汚染したりしないようにするのが目的です。アウトドアに出か ける際にはザックにしのばせておき、使用する機会をつくっておくことで、災害時にも抵抗なく使うことができます。

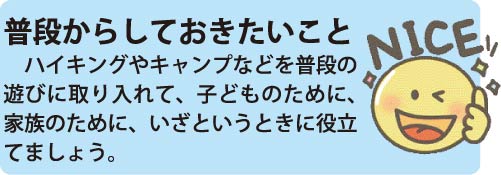
<低山へのハイキング>
災害時、がれきを乗り越えたり山道を歩いたりできるように、家族でハイキングに出かけ、不整地歩きに慣れましょう。
<キャンプの体験>
電気・ガス・水道を使わずに一晩過ごす「サバイバルナイト」お子さんがまだ小さい場合は、家の中で野外生活のまねごとをしてみましょう。非常食の賞味期限切れに合わせて行えば一石二鳥です。非常食を晩ごはんにして、味、量、食べやすさ、好みなどをチェックします。
<暗闇に慣れておく>
暗闇が苦手な子は、暗闇に慣れておくことも大切。ヘッドランプやろうそくの明かりのもとでカードゲームをして過ごすなど、楽しみながら経験を積み重ねていきましょう。
<和式トイレを子どもに使わせておく>
災害時は和式トイレしか用意できないこともあるので、遊びに出掛けた先に和式トイレがあれば、積極的に使わせておくなど、日頃から和式トイレにも慣れさせておくといいですね。
できるだけ安全に子どもを避難させる
歩ける子であっても、なるべくおんぶやだっこをして、子どもが怪我をするのを防ぎ、子どもとはぐれてしまわないように.靴は必ず履かせておきます。ヘルメットや帽子で頭も保護しましょう。避難時は、なるべく両手を空けておきたいもの.そんな時、「ベビーキャリア」があると便利.災害時にも役に立ちます。子どもの着替え、おむつ、おしりふき、タオル、ビニール袋、食料、水など、非 常時に必要なものを入れてしまっておくようにすれば、いざというとき、子どもを乗せてすぐに避難できます。
 子どもをぎゅーっと抱きしめて
子どもをぎゅーっと抱きしめて
災害が発生した日、親と離れ離れで一晩を過ごした幼稚園の子どもたちが、親に会うまで泣いたりぐずったりしなかったという話を聞きました。小さな子であっても災害という非常事態を理解し、大人たちを困らせないようにじっと我慢することがあります。
兄弟姉妹がいる場合は、上の子ほど我慢するようです。避難生活で親も精いっぱいですが、子どもたちもがんばっています。被災後は先の見えない生活が続き、子どもの相手をする余裕がないかもしれませんが、しっかり抱きしめてあげてください。上の子にも、下の子と同じように甘えさせてあげてください。
 NPO法人 森は海の恋人 畠山 信(はたけやま まこと)さんは、
NPO法人 森は海の恋人 畠山 信(はたけやま まこと)さんは、
「安心・安全」を考えるのであれば、「危ないことをしない」のではなく、「危険の感覚とそれを回避する技術の向上」を目指すべきなのだと思います。さまざまな体験を通して、その感覚と技術を学ぶべきだと思うのです。キャンプなど野外活動の知識と技術は身を守る第一歩といえます。シートとロープでタープが作れるかどうか、実際に経験しておくといざという時に必ず役に立つことでしょう。
