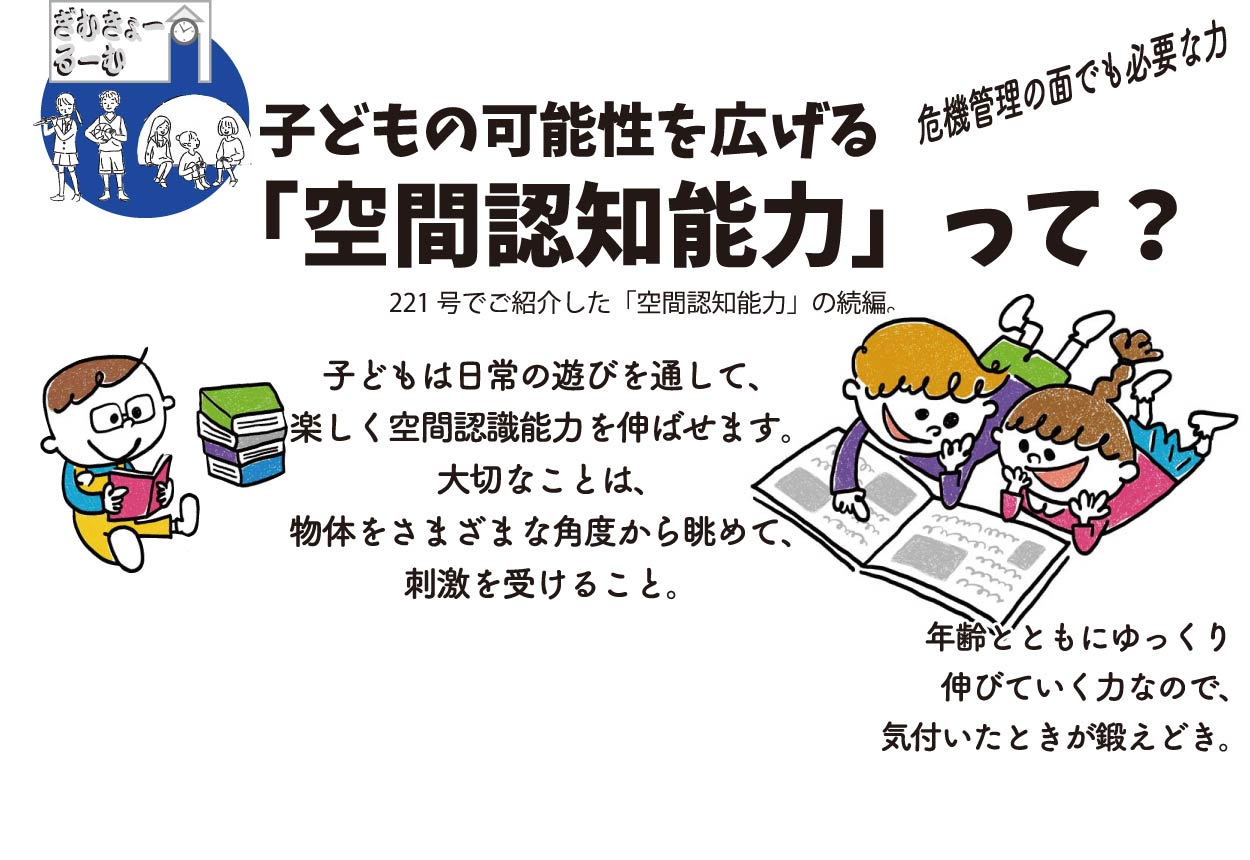

パズル
 パーツを組み合わせて完成させるパズルは、空間認知能力を鍛える遊びの一つ。パーツがどの位置にくるかを予測すれば、頭の回転が速くなります。絵柄を完成させる平面パズルだけではなく、立体のパズルにチャレンジすると、効果的に空間認知能力を鍛えられます。
パーツを組み合わせて完成させるパズルは、空間認知能力を鍛える遊びの一つ。パーツがどの位置にくるかを予測すれば、頭の回転が速くなります。絵柄を完成させる平面パズルだけではなく、立体のパズルにチャレンジすると、効果的に空間認知能力を鍛えられます。
パズルに慣れていない子どもは、簡単なパズルから挑戦してみましょう。最初に難しすぎるパズルを与えると、完成させられずに子どもがやる気を失うかもしれません。子どもの発達に合ったパズルを選ぶことで、楽しく取り組めます。
積み木・ブロック
積み木・ブロックは組み合わせることで立体を形作れる、空間認知能力を鍛えるのにぴったりの遊びです。
例えば「ロボットを作りたい」と思ったとき、ロボットの形状を思い浮かべてパーツを選び、組み上げることで、3次元空間での想像力が身につきます。
積み木・ブロックに慣れておらず、何をしていいかわからない子どもには、まずはお手本を見せながら積み木・ブロックに触れるところから始めましょう。
簡単な組み合わせを子どもと一緒に作りあげ、完成したら褒めることで子どものやる気を引き出せます。
折り紙
平面的な紙を折りあげて、さまざまな形に作り変える折り紙は、空間認知能力を上手に鍛える遊びです。
決まった折り方でオーソドックスな作品を作れるほか、自由に折ることで想像力を高められます。
子どもが初めて折り紙に挑戦するときは、手数が少ない平面的な作品を折るのが良いでしょう。できるようになったら、徐々に難易度をあげて、立体的な作品に挑戦してみましょう。
子どもが自分で折り方を確認しながら折り紙をすれば、空間認知能力アップにつながります。
外遊び(おにごっこ・ジャングルジムなど)
外で体を動かすことも空間認知能力を鍛えるのに効果的といわれています。たとえば、おにごっこは相手の位置と自分の位置を確認することで距離を把握する力をはぐくみます。
 一つ目の理由として、「空間認知能力」が高い人は「IQ(Intelligence Quotient=知能指数)」も高い傾向があると言われているためです。この相関については、学術雑誌『図学研究』に掲載された「MCT (切断面実形視テスト)によって評価される空間認知力と一般知能との関係」という論文内で報告されており、「空間認知能力」と「IQ」には、かなり高い相関が見られるそうです。
一つ目の理由として、「空間認知能力」が高い人は「IQ(Intelligence Quotient=知能指数)」も高い傾向があると言われているためです。この相関については、学術雑誌『図学研究』に掲載された「MCT (切断面実形視テスト)によって評価される空間認知力と一般知能との関係」という論文内で報告されており、「空間認知能力」と「IQ」には、かなり高い相関が見られるそうです。
また、もう一つの理由として、子どもの遊び方の変化による空間認知能力の低下が危惧されるようになったという時代背景があります。
かつての子どもたちは、外で鬼ごっこや木登りをして遊んだり、室内でも積み木や折り紙をして遊ぶなど、その遊び方は立体的なものばかりでした。しかし現代の子どもたちは、スマートフォン・タブレットを使ったゲームや動画視聴など平面的な遊びが多く、立体的な遊びをする機会が少なくなっています。
学校現場においても、見取り図や空間図形の問題が苦手な子ど
もが増えており、空間認知能力の低下や能力を鍛える機会の少なさが課題となっています。
日常生活の中で鍛える
こそあど言葉(これ・それ・あれ・どれ等)を使わず、具体的な位置や形を表す言葉を使ってみる。こそあど言葉は物体や空間の詳細をイメージしにくく、空間認知能力の成長に必要な「位置関係や形状を頭の中でイメージする」機会が損なわれてしまいます。
例えば、「これをあそこに入れておいて」と言うところを、「この本を棚の一番上の左側に入れておいて」と言ってみるとよいでしょう。上下や前後左右だけでなく、大小を意識させる声掛けもおすすめです。