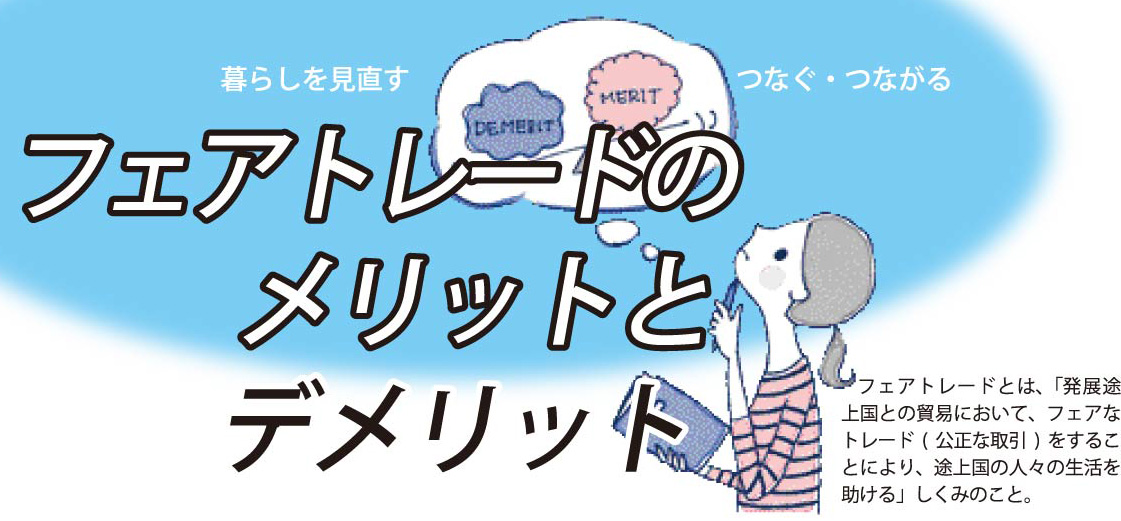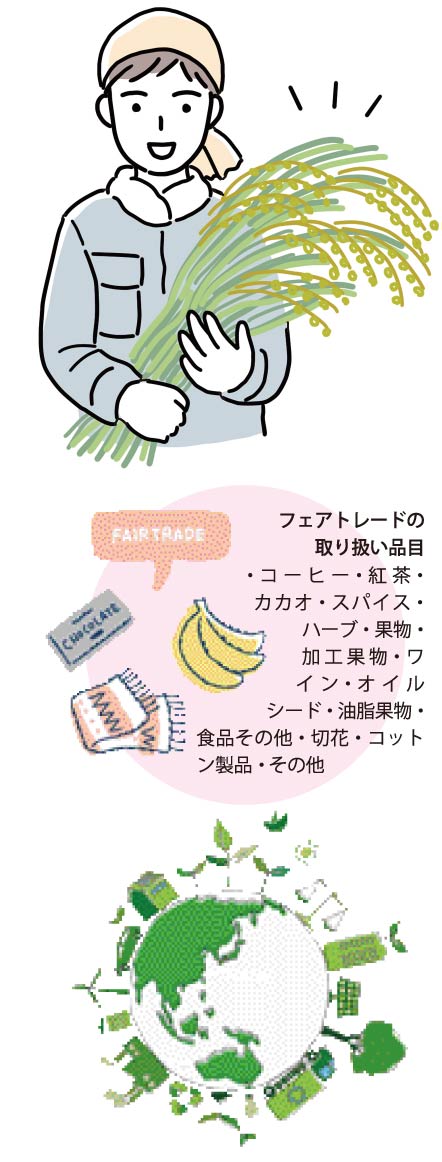
<生産者にとって>・所得を増やす機会が得られる。・生活が安定し、貧困から抜け出せる。・子どもが労働することなく教育を受けられる。
<消費者にとって>・安心・安全な商品が手に入る。・こだわりの品・質の高い商品が手に入る。
<企業にとって> ・企業のイメージアップになる。・ESG投資や株式による資金調達。
<社会や環境にとって> ・社会や環境が持続可能になる。・途上国が経済成長できる。・経済的協力関係が安定し、戦争や紛争が減る。
社会や環境にとってのメリット
発展途上国で、現地の人の収入が増えれば地域経済が成長します。フェアトレードでは地域を支援するプラスアルファのお金(フェアトレード・プレミアム)を生産者やその団体に支払うことも定められていますが、その資金で学校や病院が建てられ、くらしが安定して豊かになります。治安がよくなり、紛争や戦争につながる地域や民族のトラブルも減らすこともできるでしょう。
また、農薬や化学肥料を減らすことで生態系を守り、環境破壊を防ぐことができます。つまり、社会や環境が今もこれからも、安心で「持続可能」になるということです。
さらに、「貧困をなくそう」「質の高い教育をみんなに」「陸の豊かさも守ろう」「パートナーシップで目標を達成しよう」など、世界全体が目標にしているSDGsの実現にもなります。社会や環境が持続可能に近づくということは、わたしたち一人ひとりにとっても望ましいこと。これもフェアトレード商品を選ぶべき大きな理由となります。
フェアトレードが進まない理由とは?
生産地を助けるだけでなく消費者・企業にもメリットがあり、SDGsにも貢献するフェアトレードですが、なかなか進んでいかない現状があります。
<生産者にとって>・デメリットなし(※)
<消費者にとって>・価格が高い。・商品のバリエーションが少ない。
<企業にとって> ・コストが高くなる
<社会や環境にとって> ・デメリットなし(※)
※ただしすべてのフェアトレードが十分にうまくいっているわけではないので、個々のフェアトレード事例で問題点や改善点はあります。
社会や環境にとってのデメリット
フェアトレードのしくみは社会や環境にデメリットがないように配慮して設計されています。
しかし、フェアトレードでは市場価格とは別の価格を設定するので、自由市場経済のメカニズムが働かない場合があります。したがって、サプライチェーン(原料調達・製造・輸送・販売などの流れ)のなかでコストがかかってしまうというような問題が生じる可能性もあります。
フェアでないトレードって?
 フェアトレードをわかるにはまず「フェアでないトレード(公正ではない貿易)」について知る必要があります。貿易をする2つの国を例にとって考えてみます。
フェアトレードをわかるにはまず「フェアでないトレード(公正ではない貿易)」について知る必要があります。貿易をする2つの国を例にとって考えてみます。
A国は農地が多く小麦を生産し、B国は技術が高く自動車の生産が多かったとします。A国は小麦を、B国は自動車を相手の国に輸出することでお互いに利益を得て、A国もB国も輸出によってお金を得て、輸入でほしいものが手に入り、「貿易する前」よりも豊かになります。
まずB国はA国に「もっと生産量を増やすため」などと話をもちかけ、A国にお金を投資して大規模な農地を開発し、農機具を持ち込み、農場を経営して現地の人を雇い入れます。さらに、農園の作物をB国にとって小麦よりも輸入したいさとうきびに切り替えることもあります。そうなると、A国はB国のためにひたすらさとうきびを生産し続けることになります。
ここで生じる最も重大な問題は、A国で生産したさとうきびの価格をB国が決めてしまうということです。B国は安くとうもろこしを輸入して大きな利益を得るのに、A国は利益が得られず、現地で働く人は安い賃金でそこにやとわれて働きます。この状況はずっと続き、A国は貧しいまま、B国は貿易によってますます豊かになっていくのです。
これが、「フェアでないトレード」という不公正・不平等な現実です。「一方の国は豊かになるが、一方の国は豊かにならない」という貿易が行われているのです。
フェアトレードの始まり
始まりは、1940年代後半にアメリカのNGOがプエルトリコ(カリブ海にあるアメリカ領)の女性たちが作った手工芸品を販売したことだといわれています。当初はチャリティー活動の意味合いが強く、フェアトレードでなく「オルタナティブ・トレード」(もうひとつの貿易)と呼ばれていたようです。 1970年代に入ると、開発途上国の産品を購入することにより、こうした国の人々を積極的に支援していこうという試みはさらに広がり、「公正な価格で輸入しよう」との意味合いから「フェアトレード」という言葉が定着。やがて、工芸品・バナナ・チョコレート・コーヒー・衣類など、商品のバリエーションが増えて、欧米には「フェアトレード・ショップ」ができました。「フェアトレードがなぜ大事なのか」を広く一般の人に知ってもらおうという動きも活発になっていきました。
2000年以降になると、フェアトレードに積極的に取り組む大手スーパーや食品メーカーも増え、「フェアトレード」という言葉がようやく一般の人に知られるようになってきました。
行政でも、公正な取引で格差のない社会を実現しようとする「フェアトレードタウン」認定を目指す動きが始まり、2011年、熊本市が日本初のフェアトレードタウンに認定され、2020年9月までに名古屋、逗子、浜松、札幌、いなべ各市も認定を受けました。
社会の未来を育てるウェブメディアより