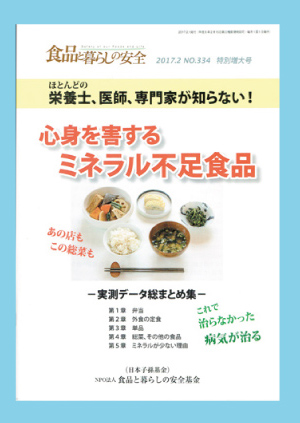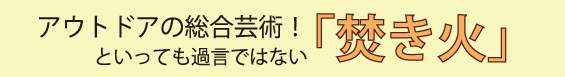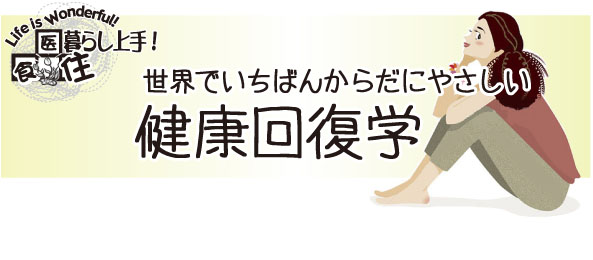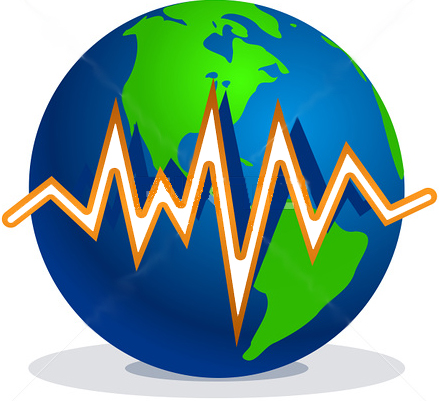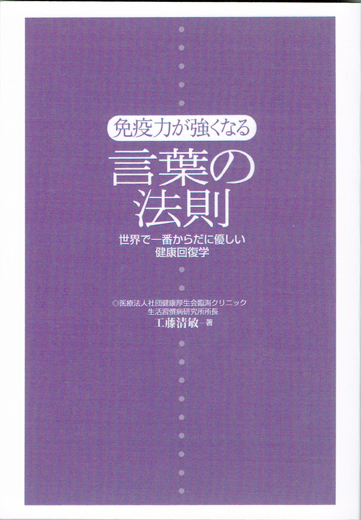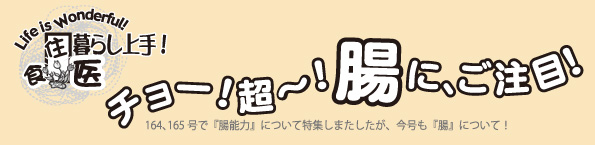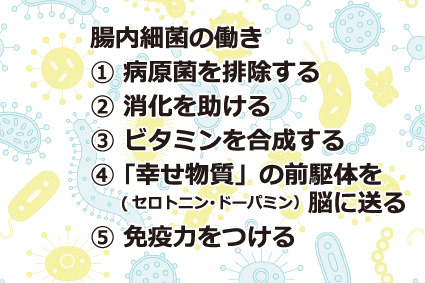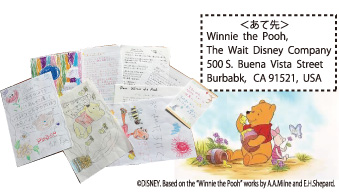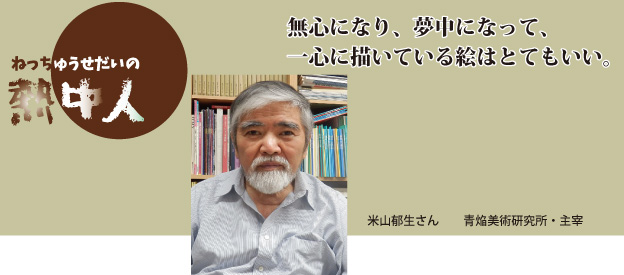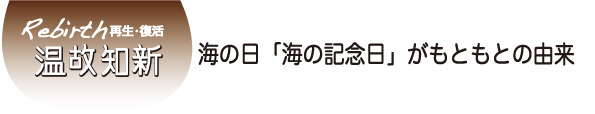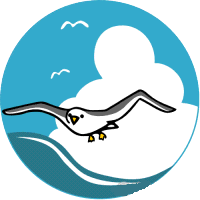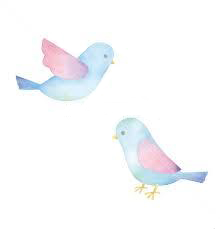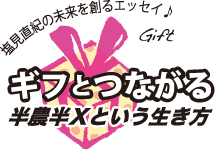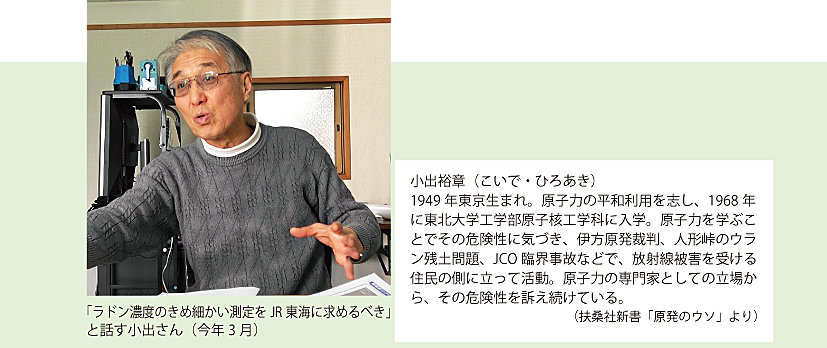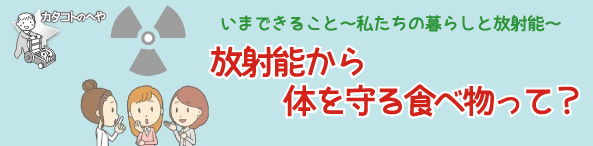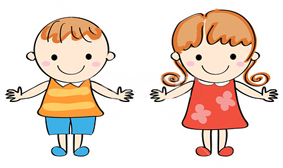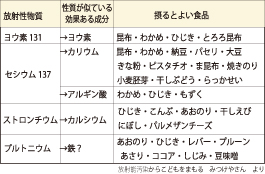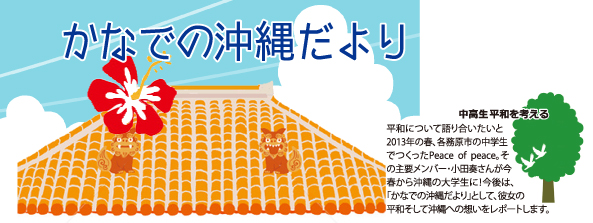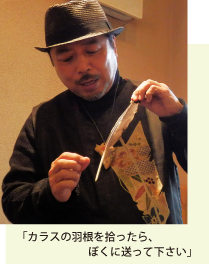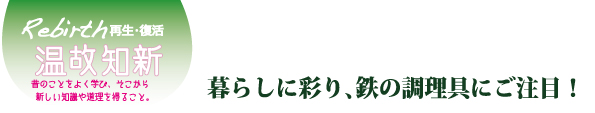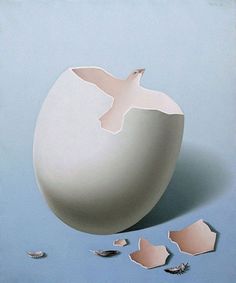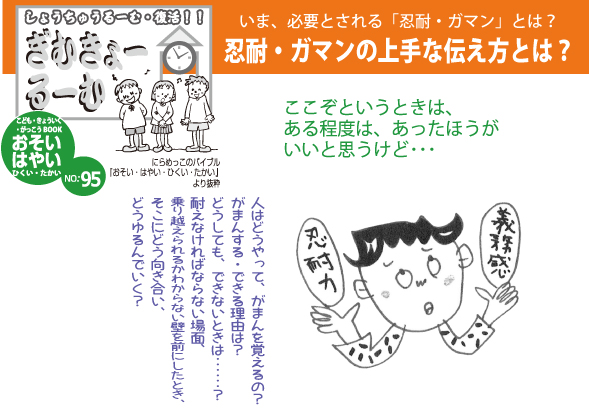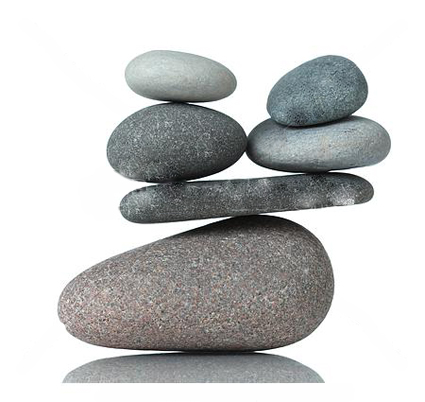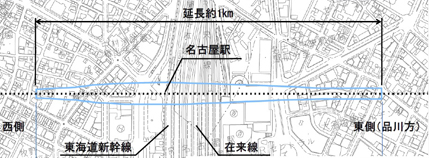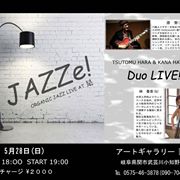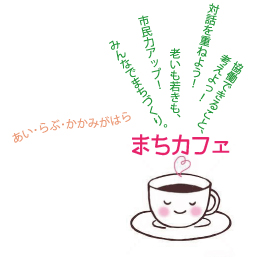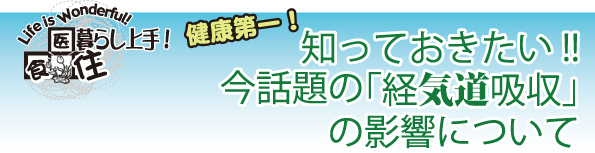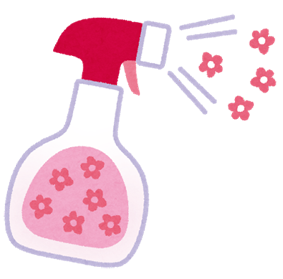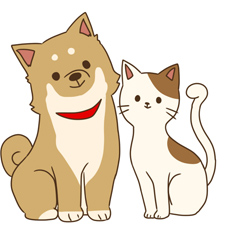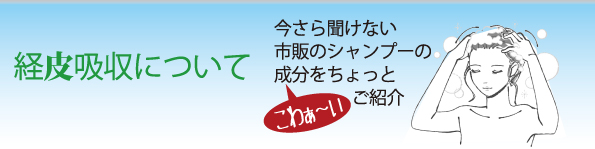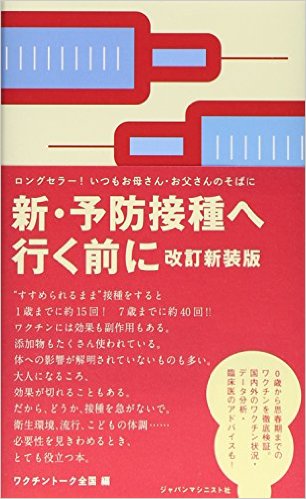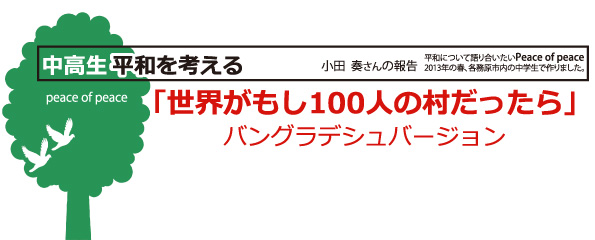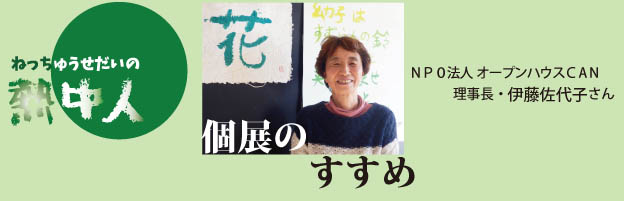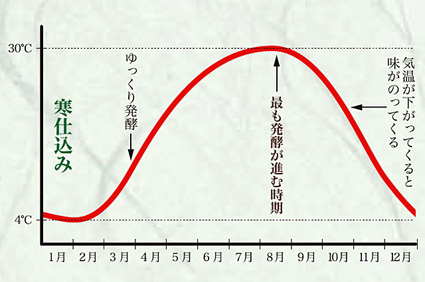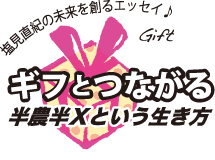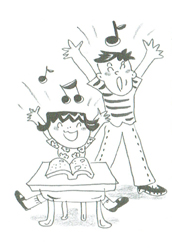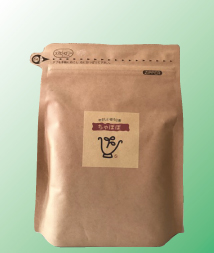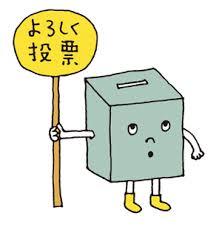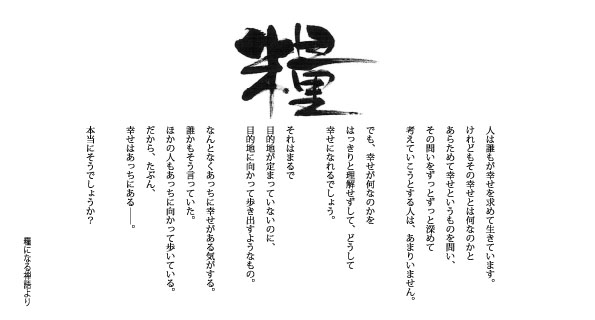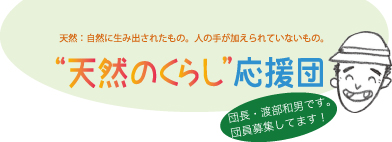
要注意!アトピービジネス
「アトピー性皮膚炎は良くなったり悪くなったりを繰り返す、かゆみのある湿疹を主な病変とする疾患」です。アトピー性皮膚炎(以下、アトピー)の患者はかゆみに苦しみ、肌をかくことで皮膚を痛めることがあります。無理解な人はそれを恐れたり、嫌がったりします。このため患者は人前に出るのをためらい、時には引きこもることさえあります。保護者の苦労も大変で、夜でさえ十分眠ることができません。
アトピーは先進国に多いといわれます。日本にも多数のアトピー患者がいますが、他の国とは異なる2つの特徴があります。それはステロイド恐怖症とそれに便乗したアトピービジネスです。ここでステロイドとはステロイド系抗炎症薬のことです。
ステロイドを恐れるのは
アトピー治療に使うステロイド外用薬は注意深く使用すると非常に有効な医薬品で、重い副作用はほとんど出ません。しかし、強い外用薬を漫然と長期間使うと、皮膚萎縮(皮膚が薄くなる)や紫斑、毛細血管の拡張、皮膚感染症などが起こることがあります。ステロイド注射薬や内服薬による副作用が、通常の外用薬使用でも生じるという誤解が一部にあります。この様なステロイドのよる副作用を1990年ごろのマスコミが取り上げ、人々はに不安になりました。この不安を「ステロイド恐怖症」と呼ぶ人々もいます。
 アトピービジネス
アトピービジネス
患者の不安につけ込む形で様々な形の商売、アトピービジネスが現れました。それはアトピーに効くという高価な水や温泉水の販売(害にも薬にもならないだけまだ良いでしょうか)や、宗教、化粧品、エステサロンなどです。アトピービジネスが好ましくないのは、(1)患者が有効な治療を受ける機会を奪い、(2)高額な治療費を出させることが多いことです。その例を少し見ましょう。
ステロイドが入っていないクリーム?
ステロイド入り化粧クリーム「NOATOクリーム」を販売したとして、警視庁は2009年8月、東京都新宿区の輸入販売会社イエス・オーケーの5人を薬事法違反の疑いで逮捕した。同社はインターネットなどで「ステロイドは一切含まないので、赤ちゃんや妊婦も使える」などと宣伝し、約4000万円を売り上げたという。「かってはステロイドが化粧品に入っていた時代がありました」と書きたいのですが、東京都は2016年5月にアトピーに効果があると宣伝するステロイドの入っていた「ばらクリーム」の製造・販売の中止をを指示しました。外国からもステロイドが含まれている類似品が入り込んでいます。
エステティックサロンでも被害が(科学的そうな説明)
過去にアトピー性皮膚炎にかかっていたが、良くなっていた女性(20)は、肌をきれいにとエステティックサロンに行った。従業員の過去にステロイド剤使用の有無を質問。女性は5、6年前まで使用していたと答えた。従業員は、ステロイド使用経験者は超音波美容器具使用によって肌の中にあるステロイドがリバウンドして症状が出ることがあるが、3カ月後には治ると説明。超音波による顔面エステを受けたが、翌日顔が赤く腫れ、かゆみを感じた。エステ店店長はステロイドによるリバウンドで、3カ月の辛抱だという。アトピーが体にも出てきたので相談すると、従業員は血液が流れているから体にも出ると答え、ストロイド剤の悪影響を繰り返し説明した。3カ月というのはエステエキスなどを飲めば3カ月で治るのだといわれ、高価な品を購入した。
その後1年半たっても悪かったので、皮膚科の診察を受け、ステロイドやアトピー性皮膚炎の説明を受け、ステロイドを使用する治療を受けた。エステティックサロンに損害賠償を請求し、2001年東京地裁で勝訴し、高裁で和解。(国民生活センター、2003年)。
医学界の対応
医学界は自分らにも責任があるこの様な状態の是正に取り組んでいます。日本皮膚科学会は「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2016年版」を発行し、適正な治療の進め方を示しました。さらに、アトピー患者や保護者が病気や治療を十分理解できず不安を持つので、適切な治療ができていないと認め、医師などによる複数回の患者教育の必要性に気づき、患者が治療方針を守れる方策を考え、ステロイド以外の新しい医薬品も示しました。
困った時は、思い出して下さい。
・ステロイド外用薬は炎症をなくし、 アレルギー反応を抑える即効性が ある薬です。通常のステロイドに 重い副作用はありません。
・信頼できる専門病院に行き、良く 相談し、説明を良く聞いて下さい。
・科学的と思えるような説明でも、 うかつに信じるのは止めましょう。
・インターネットや雑誌などに出て くるうわさや宣伝などは鵜呑みに しないで下さい。
わたなべかずお:福島県生まれ。新潟大学卒。浜松医科大学勤務(脳研究と教育に従事)医学博士、各務原ワークショップ主宰(毎月第4木曜日13:00〜渡部宅(各務原市蘇原東栄町)主に健康と環境に関することの勉強会)参加希望者はbandaikw@sala.dti.ne.jpまで